 2024.12.20
2024.12.20
 演習の位置づけは、講義で学習した内容を、プレゼンテーション、ディスカッション、ロールプレイをとおして、援助場面で活用できることを目指します。
ソーシャルワーク実践の基礎となる視点と技術を学ぶとともに、利用者理解の視点を修得することも指しています。
演習の位置づけは、講義で学習した内容を、プレゼンテーション、ディスカッション、ロールプレイをとおして、援助場面で活用できることを目指します。
ソーシャルワーク実践の基礎となる視点と技術を学ぶとともに、利用者理解の視点を修得することも指しています。
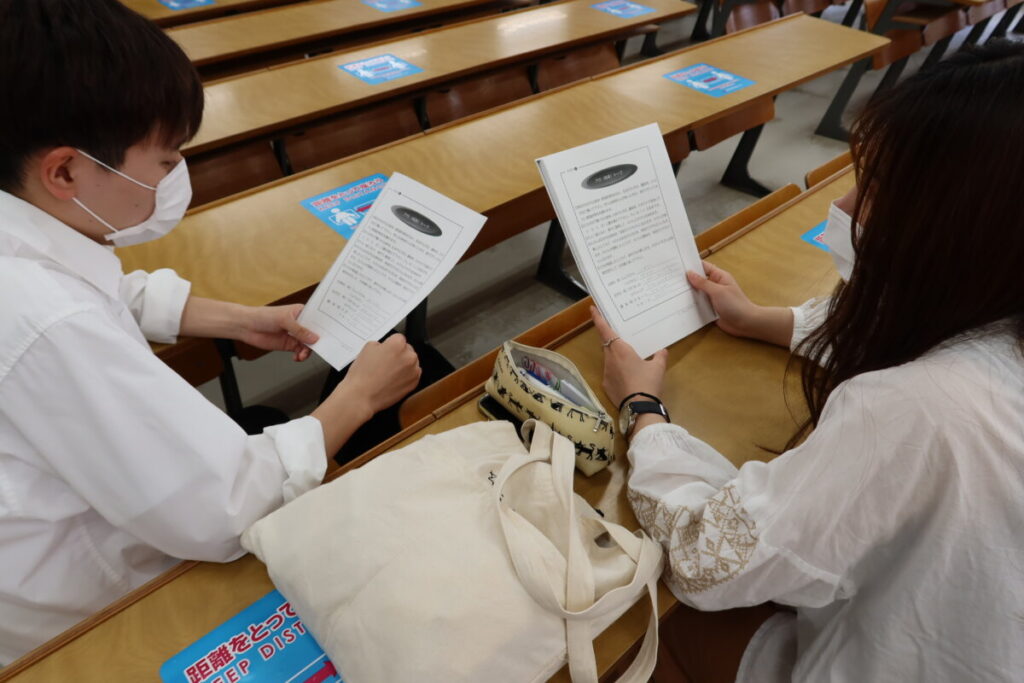 この日のワークは「共有しようとする意欲」について取り上げました。
送り手が発することができる言葉は「母音(あいうえお)」のみという条件をつけた上で、自分の出身地や趣味などを相手学生に伝えます。
受け手の学生は適切な反応をしながら、相手学生の伝えたい内容を理解できるように努めます。
この日のワークは「共有しようとする意欲」について取り上げました。
送り手が発することができる言葉は「母音(あいうえお)」のみという条件をつけた上で、自分の出身地や趣味などを相手学生に伝えます。
受け手の学生は適切な反応をしながら、相手学生の伝えたい内容を理解できるように努めます。
 取り組んだ学生は、「正解がわからないので何度も聞き返した」「伝わったときの相手の反応を見ると達成感を感じた」などのコメントが聞かれていました。
これらのワークをとおして具体的な援助場面をイメージし、コミュニケーション力や思考力・共感力などを高めていきます。
取り組んだ学生は、「正解がわからないので何度も聞き返した」「伝わったときの相手の反応を見ると達成感を感じた」などのコメントが聞かれていました。
これらのワークをとおして具体的な援助場面をイメージし、コミュニケーション力や思考力・共感力などを高めていきます。

